3 勉強
塾にも行かず、通信教育もせずに4か月で合格した勉強法や、使った教材を紹介します。自分の中では合格という結果に結びついた勉強法なのでよいものだと思います。しかし、勉強法は人によって最適なものが異なるのであくまで参考にしてください。
3-1 これまでの勉強
4か月で合格したといっても4か月は受検勉強をした期間であって、勉強自体は保育園に通っていたころから続けていました。毎年第1回の漢検での満点合格を目指して漢字練習をしたり、数検の満点合格を目標にして勉強したり、さらに高いレベルの学力をつけるために日能研の全国テスト(無料で誰でも受験できる)を定期的な目標にして、読解問題や文章題や計算問題を毎日やっていました。たまに私立中学校の入試で出題されるような問題にも取り組みました。その他の教科や適性検査で出題されるような総合的な問題や記述式の問題などはやっていませんでした。
このころはまだ勉強を進んでやることは多くはありませんでした。「計画を立てて勉強しなさい」といつも父に言われていたのですが、何日でこの問題集を終わらせるかということしか考えていませんでした。毎日、朝起きてからの時間と放課後図書館へ行き、そこでの時間合わせて2時間半を勉強時間と決めていました。しかしその通りに勉強しない日もあり、6年生になると日能研の全国テストもなくなったため、ダラダラ勉強していたので受検勉強を始めたばかりのころはスムーズに進んでいきませんでした。
3-2 使った教材
使った教材を紹介します。塾に通わず4か月という短期間で最大の効果を上げるには、自分が必要としている力が身につくような教材を選ぶことが大切で難しいことでした。
まず初めに、朝日学生新聞社が出版している公立中高一貫校適性検査対策問題集の5冊シリーズ(作文力で合格、作文力で合格2、思考力で合格、考察力で合格、分析力で合格)をやり、どの分野もある程度の答案が書けるようになりました。このシリーズは解答例がたくさん載っていて(作文の2冊)色々なテクニックや構成を自分のものにできました。
それぞれの解説も充実しているので、受検勉強を始めたばかりの人はこのシリーズをやるとよいと思います。
次に弱点だと判明した社会分野を鍛えるために、東京学参の『公立中高一貫校適性検査対策問題集資料問題編』と、朝日学生新聞社の『グラフ問題特別ゼミ』に取り組みました。朝日学生新聞社の『グラフ問題特別ゼミ』はグラフの読み方、答案の書き方、グラフの種類とその特徴や読み取るべきことなどが例題とともに解説してありとても分かりやすく、上達していきました。この教材はグラフ問題が苦手な人にお勧めです。
東京学参の『公立中高一貫校適性検査対策問題集資料問題編』は難しい問題も載っているので、実戦力をつけるために2回やりました。
そして、すべての分野をまんべんなく学ぶために文理の『適性検査対策問題集』をやりました。ちなみに過去問題集は東京学参の『都立立川国際・南多摩中等教育学校』を使いました。
3-3 見直しノート
見直しノートとは、その日に解いた問題の要点をまとめたノートのこと。本番前に見直しをするために作っていきました。間違えた問題はもちろんのこと、正解した問題もまとめました。しっかり説得力のある答案を書くには、知識だけではなく思考力や考察力、作文力が必要になるので、順序立てて解く方法やキーワード、考え方など様々なことを書いていきました。どんどん脱線して知識を広げていくことも大切です。全ての問題に共通する解き方(グラフの読み方、書く項目、答案の書き方など)も書きました。
自分にとって最適な見直しをしたいときは、自分のことを一番よく知る自分が作ったノートが強力な武器になります。そこで、このホームページを読んでいる人には見直しノートを作ることをお勧めします。もし作るのであれば、問題を解き答え合わせをする時間と同じくらいの時間を費やしても良いと思います。受験勉強に限らずすべての勉強に用いることが可能なので、これからも続けていこうと思います。
3-4 作文指導
適性検査Ⅰの7割を占めている作文ですが、自分では添削できないので父に添削や指導をしてもらいました。一つ一つの作文に対してとても細かく添削してくれました。「いりたまご」を主な採点基準として、さらに構成力もチェックしてもらいました。書き始める前に構成を考えること、問に正面から答えること、上手く接続語を使って段落の間に関連性を持たせること、まとめをまとめらしくしっかり、厚く、1段階高いところから考えて書くこと。その他にも表現や具体例のこと、改善すべき部分、プラスアルファでさらに得点を積み上げられる部分などたくさんのことについて指導してもらいました。常にとても厳しいスパルタ指導だったけれど、父のおかげで合格でき、論理的な考えもできるようになり本当に感謝しています。
見直しノートに書いたことも紹介します。作文問題はほとんどの場合経験を書くので、テーマごとに経験を書き溜めていきました。教えてもらったことを自分の言葉にして書いていきました。解答例から良い構成や表現を書き出していくことや、上手く書けた作文の要約をして今まで学んだことを再確認して試験前の10日間程を過ごしました。あと10日にもなると、そこから新しいことを詰め込んでも身につかないと思ったので、見直しと感覚を忘れないために書きやすい作文問題に取り組んでいました。
父に指示されたことを一つ一つクリアしていくうちに、作文はどんどん上達していきました。
3-5 適性検査Ⅱ
適性検査Ⅱの対策として主に算数分野、理科分野、社会分野を勉強しました。算数の勉強は以前からしていたので苦戦しませんでしたが、初めて勉強する理科分野、社会分野は苦戦しました。特に、社会分野のグラフなどの資料を読み取る問題が苦手で特訓しました。
問題を解くとき実践したことは、時間を決めて取り組むということです。なぜなら、適性検査は45分しかないのでスピーディーに問題を解くことが求められるからです。しかも、効率よく勉強することにもつながります。問題を解くことになれたらやってみてください。時間の過ぎ行く感覚も分かります。
見直しノートも作りました。適性検査はただ答えを出すだけなら簡単な問題が多いですが、解き方を説明することが簡単ではないので、見直しノートには順序立てて書いていくことを意識しました。
算数分野は、図形やゲームに絡んだ問題が多かったので図を描きながら整理していきました。
理科分野は、実験結果から考察する問題が多く、必要なキーワードや数値、自分が考えたことをしっかり書いていきました。
社会分野は、出題されたテーマを自分なりにまとめたり、さらに調べたりして、初めは点のような状態だった知識を網のようなつながりあった知識に変えていきました。
適性検査Ⅱは、得点が2倍に換算されるので合否を大きく左右します。その適性検査Ⅱで高得点を取るには、限られた時間の中でいかに自分の弱点をなくすかがカギになります。弱点を克服するにはほかの分野に余裕がある必要があるので、満点を取れる分野を2つ少なくても1つは持っておいたほうがいいと思います。自分の弱点を明確にするためにも見直しノートを作ってみてください。
3-6 ena模試
毎年enaから南多摩中等教育学校の定員の6割にあたる100人ほどが合格しています。そこで、enaの模試、都立中学校別合判を受けました。
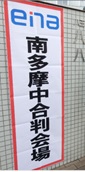
塾に通っていない自分の実力がどれだけ通用するのか知る絶好の機会でした。かなりハイレベルで、実戦に近い問題に取り組めるので本番の時間配分を考える訓練になります。また、弱点が浮き彫りになるので、その後の受検勉強に生かせます。模試の当日にもらえる解答・解説が丁寧で分かりやすく、見直しノートにまとめやすかったです。2回実施され、第1回はB判定。第2回は適性検査Ⅰは77点、適性検査Ⅱは51点でギリギリのA判定でしたが、成績優秀者名簿に総合15位でのり、自信になりました。